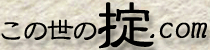普段なにげなく見ているナンバープレートの文字や数字、色などが表す意味をご存知でしょうか。ここではナンバープレートの種類や色、意味についてご紹介します。
ナンバープレートの種類や色、意味など
ナンバープレートの読み方
スポンサード リンク
ナンバープレートの正式名称は実は車両の種類ごとに違います。
登録自動車につけるナンバープレートの正式名称は「自動車登録番号標」、軽自動車・自動二輪車は「車両番号標」、小型特殊自動車・125cc以下の原付などは「標識(地方税の課金のためのもの)」です。
日本国内の公道で走行する自動車には、車両の前後に必ずナンバープレートをつける事が義務付けられています。
ナンバープレートに記されている文字と数字は、実は様々な情報を含んでいます。
まずは、ナンバープレートに記されているそれぞれの文字の呼び方をご紹介します。
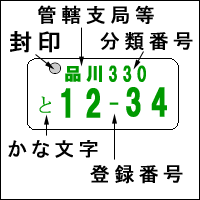
封印:ナンバープレートを取り外せないように、車両後部のナンバープレートを取り付けているネジをガードするために取り付けられる。
管轄支局等表示文字:管轄の運輸局、または自動車登録検査事務所の該当地域を表す文字。
分類番号:自動車の種別による分類番号(詳しくは後述)
かな文字:事業用、自家用、貸渡用(レンタカー)、駐留軍人、軍属私用、など使用用途に対応したひらがな1文字(詳しくは後述)
登録番号:「1」から「99-99」までの数字。希望の番号を選ぶこともできる(詳しくは後述)
分類番号の詳細は以下の通りです。
| 自動車の種類 | 割り当てられる分類番号 |
|---|---|
| 普通貨物自動車 | 1、10〜19、100〜199 |
| 普通乗合自動車 | 2、20〜29、200〜299 |
| 普通乗用自動車 | 3、30〜39、300〜399 |
| 小型貨物自動車 | 4、40〜49、400〜499 6、60〜69、600〜699 |
| 小型乗用自動車 | 5、50〜59、500〜599 7、70〜79、700〜799 |
| 特殊用途自動車 | 8、80〜89、800〜899 |
| 大型特殊自動車 | 9、90〜99、900〜999 |
| 大型特殊自動車 (建設機械) | 0、00〜09、000〜099 |
かな文字の詳細は以下の通りです。
| 自動車の用途 | 割り当てられるかな文字 |
|---|---|
| 自家用 | さ、す、せ、そ、た、ち、つ、て、と、な、に、ぬ、ね、の、は、ひ、ふ、ほ、ま、み、む、め、も、や、ゆ、ら、り、る、ろ |
| 事業用 | あ、い、う、え、か、き、く、け、こ、を |
| 貸渡用 (レンタカー) | わ、れ |
| 駐留軍人・ 軍属私用 | よ、E、H、K、M、T、Y、など |
なお、「お、し、へ、ん」は使われていません。
分類番号とかな文字について、軽自動車や自動二輪は上記と少し違う割り当てとなっていますが、ここでは割愛します。
プレートの色と登録番号
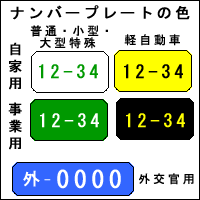
ナンバープレートの色は、自家用か事業用か、また普通車か軽自動車か、などによって決められています。
各色は右図のように、自家用であれば「白地に緑」または「黄色時に黒」、事業用であれば「緑時に白」または「黒字に黄色」となっています。
変わったところでは、外国の外交官が乗る車用の「青地に白」というものもあります。
次に登録番号についてご紹介します。
かつて登録番号は、運輸局に割り当てられたものをそのまま取り付けるしかなかったのですが、1999年から希望番号制度が導入され、自分の希望する番号を選べるようになりました。
希望番号制度は分類番号が3桁のナンバープレートを登録時に所定の手数料を支払うことで利用できます。
なお、人気の高い番号は抽選が行われています。毎週月曜日から金曜日までの受付分を翌週月曜日に抽選しています。
一般に払い出された番号なのか、希望番号制度を利用して選んだ番号なのかは、分類番号の下2桁で判別できます。
分類番号の1桁目は、いわゆる「3ナンバー」とか「5ナンバー」といった自動車の大きさや排気量に応じた番号がつきますので、必然的に希望番号制度を利用するときは分類番号は3桁のものになります。
希望番号制度で取得したナンバープレートの分類番号の下2桁には30から98が割り当てられますが、番号を使い切ったときなど、色々と細かい決まりはあります。
スポンサード リンク
スポンサード リンク